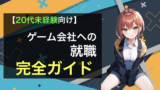・ゲーム業界のことを知りたい
・ゲームを作って稼ぐ仕事をしたい
・どんなキャリアパスがあるのか知りたい
この記事ではゲーム業界の知識と
どんなキャリアパスがあるのかが分かります。
「ゲームを作る仕事がしたい!」という漠然とした夢を
「こんな会社でこの職種になって、このくらい稼ぐ」という
具体的な内容が分かるくらいまで解像度を上げることが出来ます。
ぜひ読み進めてみてください。
本記事を書いている自分は
・ゲーム業界未経験
・大学を卒業してどこにも就職出来なかったニート
・毎日親の金で酒を飲んで何もしない
という状態でした。
そこから今では
・大手や中小合わせたゲーム会社5社を経験
・年間売上100億円規模タイトルのゲームディレクター
・数々の中途や新卒を採用する面接官
を経験しています。
私も最初は未経験で、しかも他の人と違ってニートという絶望的状況でした。
そんな状況で就活をする中で、ゲーム会社に入りたいけど
そもそもゲーム業界のことを全然知らないので、
面接をする以前に書類で落とされるということが多々ありました。
結果的にゲーム会社には受かったので、ニートというのは関係なく
本当に「こいつ何も知らないのに受けてるな」というのが伝わったからでした。
面接をする以前に足切りされるというのは
この記事を読んでまず無くしていきましょう!
ゲーム業界とはどんな世界か?
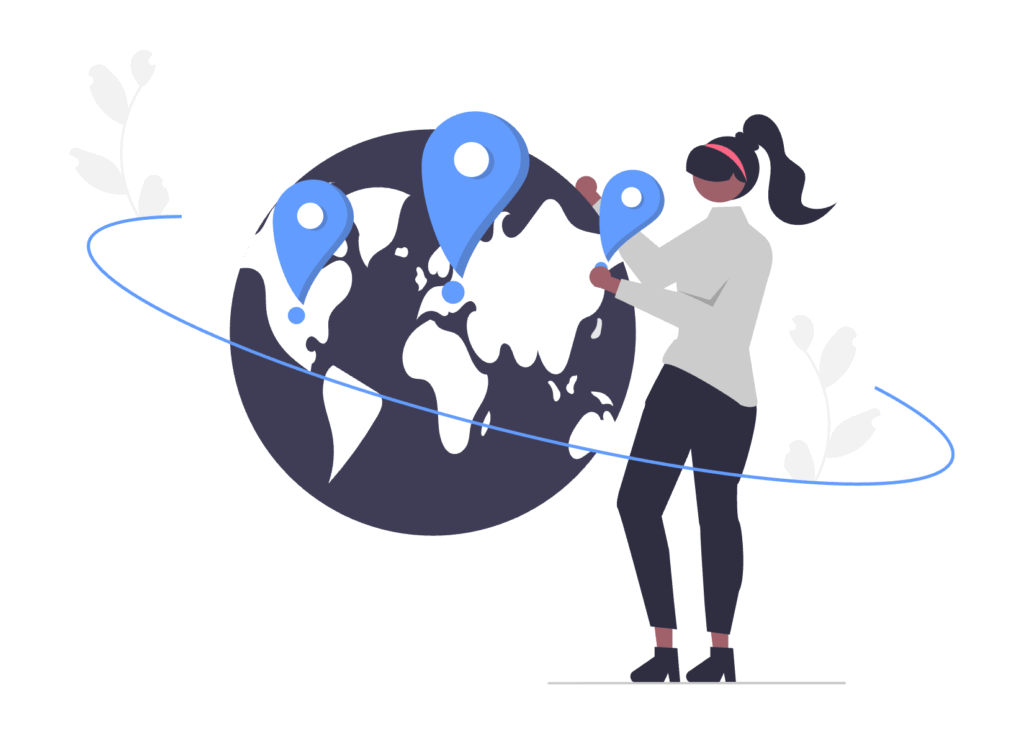
日本と世界のゲーム市場の規模
ゲーム市場は日本国内にとどまらず、世界中で拡大を続ける巨大な産業です。
特にモバイルゲームの台頭により、年々市場規模は伸びており、2020年代には世界で20兆円を超えるとも言われています。
日本でも依然として高い市場価値を持ち、世界的なIPやクリエイターも多く存在します。
ゲームは今や「エンタメ」だけでなく、「ビジネス」としても注目される分野です。
コンシューマ・モバイル・PCゲームの分類
ゲームには大きく分けて、家庭用ゲーム機で遊ぶ「コンシューマゲーム」
スマートフォン向けの「モバイルゲーム」
そしてPCでプレイする「PCゲーム」
の3種類があります。
それぞれに特化した開発会社やユーザー層が存在し、
ビジネスモデルや収益構造も異なります。
たとえば、モバイルゲームは基本プレイ無料+課金モデルが主流であり、
PCゲームは高性能を活かしたリッチな表現が魅力です。
業界における職種と会社の分類とは
ゲーム業界には多様な職種と会社の形態があります。
開発を担当する「デベロッパー」
販売・マーケティングを担う「パブリッシャー」
両方を行うハイブリッド型企業など、役割ごとに組織が分かれています。
また、職種もプランナー・プログラマー・デザイナー・サウンド・QA・マーケターなど多岐に渡ります。
作品づくりは一人では完結せず、チームによる連携が不可欠です。
デベロッパーとパブリッシャーの違い
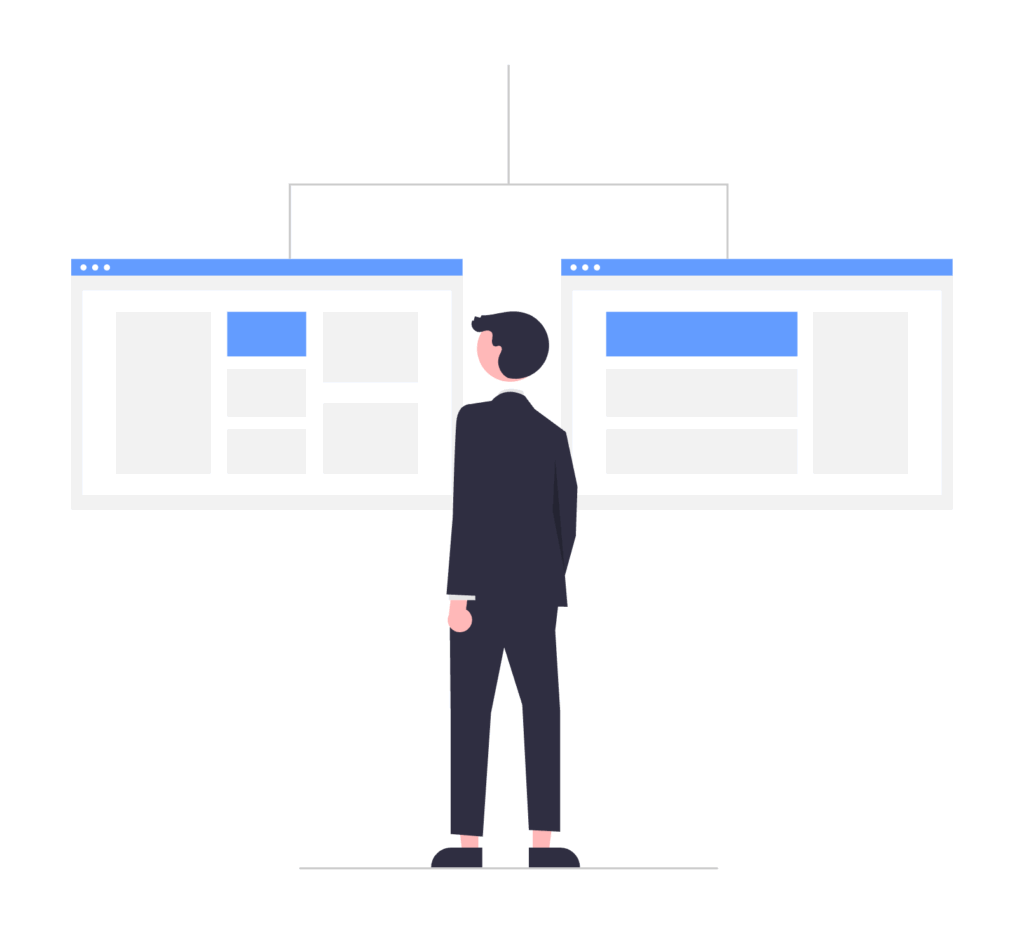
デベロッパーは「作る」会社
デベロッパーは、ゲームの企画・開発を専門に行う会社です。
ゲームの仕様設計、プログラミング、デザイン、サウンド制作などを担当し、
アイデアを実際の作品として形にする役割を担います。
中にはオリジナルタイトルを開発する会社もありますが、
多くはパブリッシャーから依頼を受けて、共同でプロジェクトを進めることが一般的です。
現場感のある制作業務に携われる点が大きな魅力です。
有名な会社だと、「ゲームフリーク」はデベロッパーになります。
パブリッシャーは「売る・届ける」会社
パブリッシャーは、開発されたゲームを市場に流通させ、
販売戦略やプロモーション活動を行う会社です。
資金調達やスケジュール管理、広告、広報、イベント企画なども担い、
ゲームを成功に導くビジネス面での責任を負います。
また、ユーザーの動向を分析して改善提案を行う役割も重要です。
売上やブランド力に直結するため、経営的視点が求められます。
有名な会社だと、「アニプレックス」はパブリッシャーになります。
どちらに就職するべきか?それぞれの特徴と働き方
デベロッパーは開発現場での実務に関われるため、
「ものづくり」を追求したい人に向いています。
一方、パブリッシャーはマーケティングやプロデュースに関わる機会が多く、
プロジェクト全体を俯瞰して動かしたい人に適しています。
どちらもゲームづくりに欠かせない存在であるので、
どちらも経験してみてから、自分に合っていると思う方を選びたいですね。
ゲームを作る仕事の職種と役割
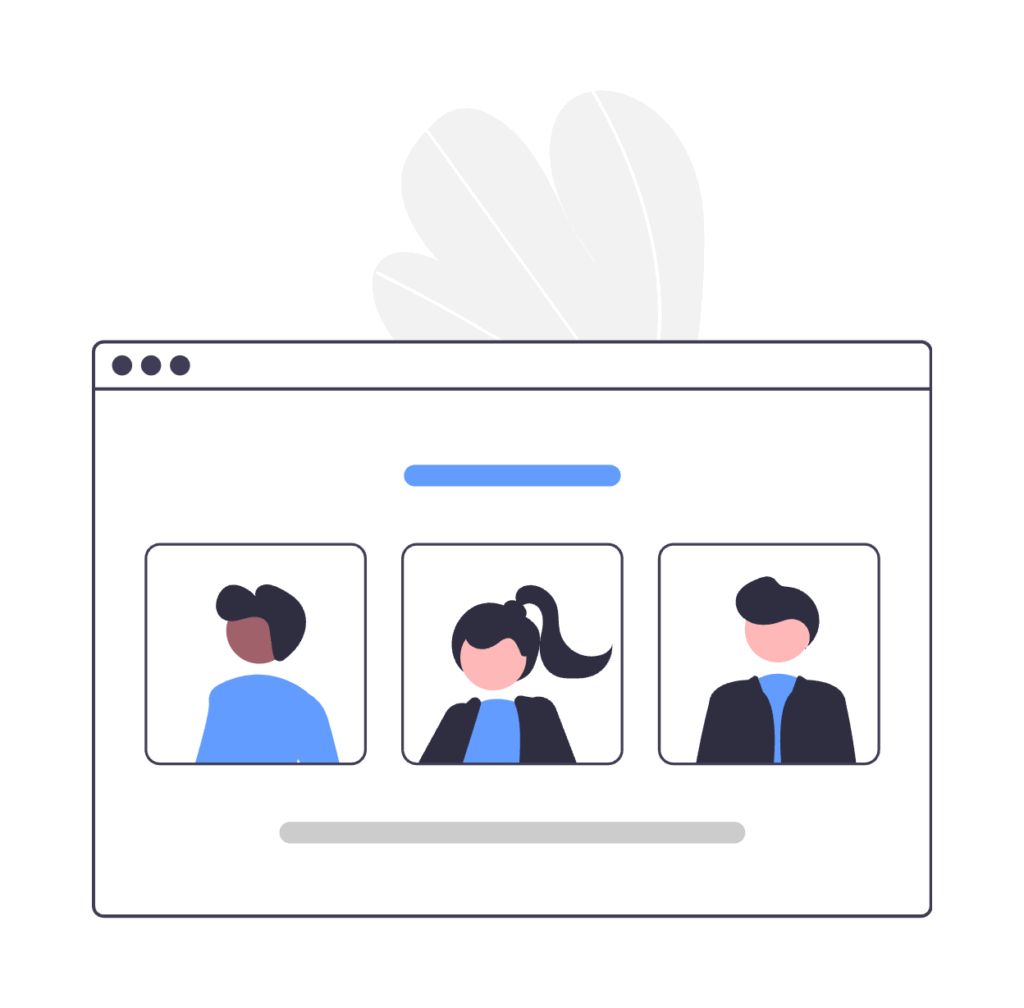
プランナー:ゲーム全体を設計する司令塔
プランナーは、ゲームの企画立案から仕様書の作成、
各セクションとの調整までを担当する職種です。
ゲームのコンセプトやルールを定め、チーム全体の方向性を示します。
仕様書を通じてデザイナーやプログラマーと連携し、
設計したアイデアを実際のゲームに落とし込む司令塔のような存在です。
ゲームの面白さを左右する重要な役割を担っており、論理的思考力とユーザー目線が求められます。
プログラマー:仕様を形にする技術の核
プログラマーは、プランナーが作成した仕様を実際に動く形にするためのコードを書く役割を担います。
ゲームのシステム開発、バグ修正、ツールの開発など、技術面の中核を担う存在です。
処理速度や安定性に関わる部分も多く、プレイヤー体験に直結する重要な職種です。
UnityやUnreal Engineなどのゲームエンジンや、C#・C++などのプログラミング言語のスキルが必要とされます。
デザイナー:ビジュアルを創るクリエイター
デザイナーは、ゲーム内に登場するキャラクター、背景、UI(ユーザーインターフェース)など、視覚的要素の制作を担います。
2D・3Dいずれのデザインスキルも求められ、世界観や没入感を左右する存在です。
プレイヤーの感情を動かすビジュアルを形にする役割であり、アートと技術の両立が求められます。
ユーザーのプレイ体験をデザインで豊かにする重要なポジションです。
サウンド、QA、マーケなど専門職の連携も重要
ゲーム制作にはプランナーやプログラマー、デザイナー以外にも多くの専門職が関わっています。
たとえば、BGMや効果音を作る「サウンドクリエイター」
ゲームの不具合を発見・報告する「QA(品質管理)」
ゲームの認知拡大や販売戦略を担う「マーケティング」などです。
これらの職種が密に連携することで、完成度の高い作品が生まれます。
多職種が関わる総合芸術としての側面を持つのが、ゲーム開発の魅力です。
その分、非常に難しい…
ゲーム業界で働くことで得られるもの
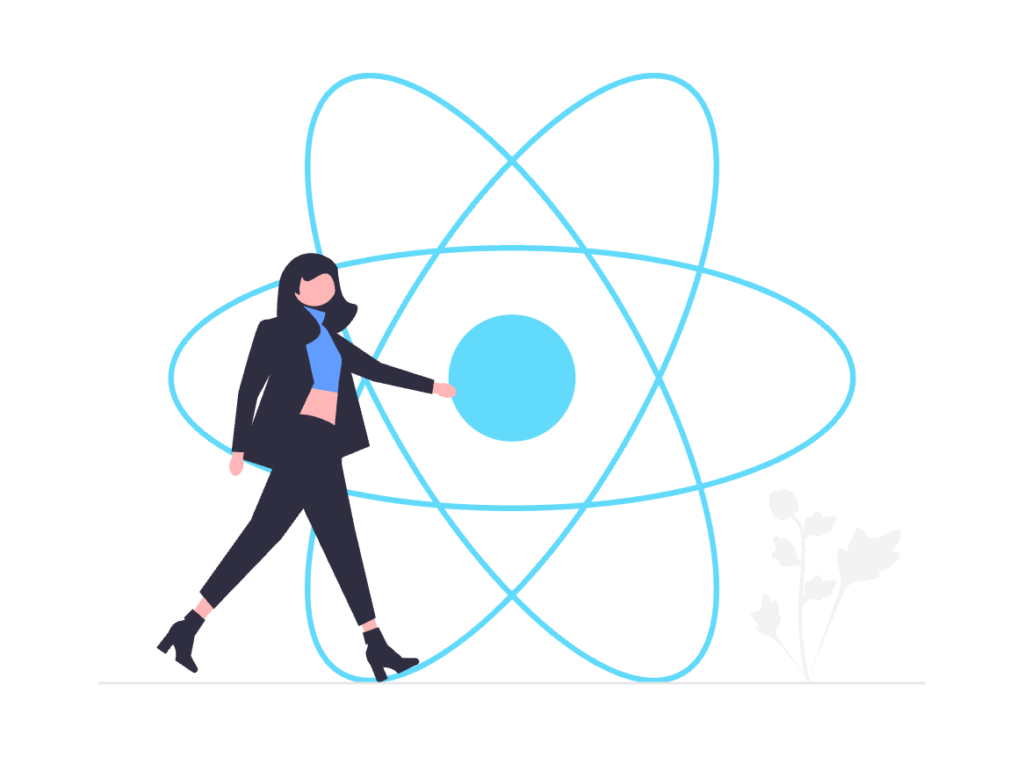
自分の手でエンタメを生み出すやりがい
ゲーム開発は、自分が作ったアイデアやシステムが、数多くのプレイヤーに届けられるという大きなやりがいがあります。
作品を通じて「面白かった」「感動した」といった感想が届くこともあり、
ものづくりの達成感を強く味わえる仕事です。
特に自分が関わったゲームが話題になったときの喜びは大きく、クリエイターとしての自信にもつながります。
スタッフクレジットに載って永遠に刻まれるのも、この世に爪痕を残した実感があって好きです。
実力主義と成果評価のカルチャー
ゲーム業界は、他の業界と比べて比較的実力主義の傾向が強く、
若手でも結果を出せば大きな仕事を任されることが少なくありません。
成果が目に見えやすいプロジェクト型の働き方であるため、
自分の貢献が直接評価に反映されやすい環境です。
一方で、スキルの差が明確になる場面も多く、自分の実力を常に磨き続ける姿勢が求められます。
成功すればインパクトも収入も大きい
ヒット作に関わることができれば、会社の業績や自分の評価にも大きなインパクトを与えることができます。
収益が大きく跳ね上がることもあり、
プロジェクトに貢献したスタッフにインセンティブが支払われるケースもあります。
さらに、業界内での実績が認められると、転職時の年収アップや独立後の仕事にも好影響をもたらします。
一生の資産になってくれるわけですね。
ゲーム業界で稼ぐために知っておくべきこと
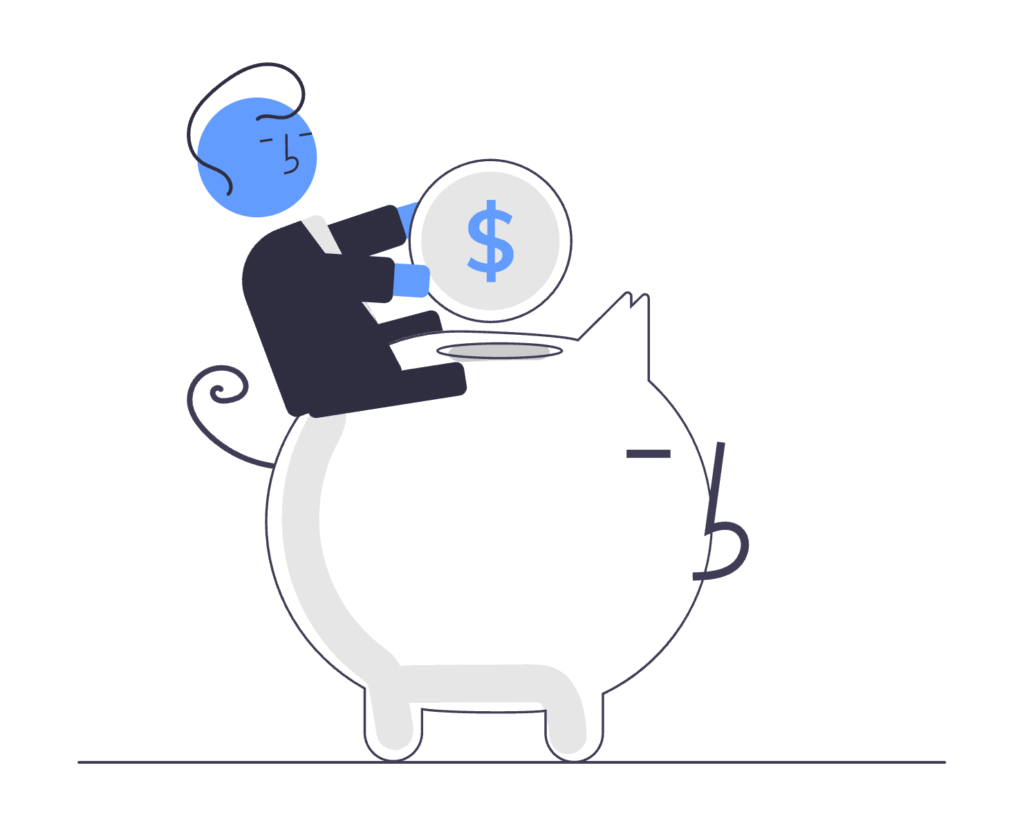
年収水準と職種ごとの報酬モデル
ゲーム業界の年収は、職種や経験、関わるプロジェクトによって大きく異なります。
たとえばプランナーやデザイナーは年収400~600万円が平均ですが、
リード職やプロデューサークラスになると1,000万円を超えることも。
また、プログラマーは技術難易度が高く、他業界からの引き抜きも多いため、比較的高水準。
成果報酬や特別ボーナスのある企業では、ヒット作で年収が跳ね上がることもあります。
収入面でのアップサイドがある一方で、
若手や下請け構造にあると水準が低くなる傾向もあるため、
企業選びは慎重に行う必要があります。
働き方とキャリアパス(社内/転職/独立)
キャリアの歩み方も多様です。
企業内で出世していく社内昇進型のほか、
スキルを磨いて他社に転職しながらステップアップしていく方法、
フリーランスや起業という道もあります。
中には、副業でインディーゲームを開発して話題を呼び、
そこから独立したクリエイターもいます。
自分のスキルをどう磨き、どう活かすかによって、柔軟な働き方が可能です。
業界特有の流動性の高さを活かして、自分なりのキャリアを描くことができます。
ブラックと呼ばれる要因と実情
「ゲーム業界はブラック」というイメージがつきまとう背景には、
納期との闘いや長時間労働の実態があります。
特に開発フェーズの終盤では、スケジュールの乱れが現場にしわ寄せされやすいのが実情です。
ただし、働き方改革の流れやテレワーク導入、プロジェクト管理の改善により、環境は徐々に良くなっている企業も増えています。
ブラックかどうかは企業体質による部分も大きいため、
就職前に評判や社風をリサーチしておくことが重要です。
ゲーム業界に入るには?未経験者の第一歩
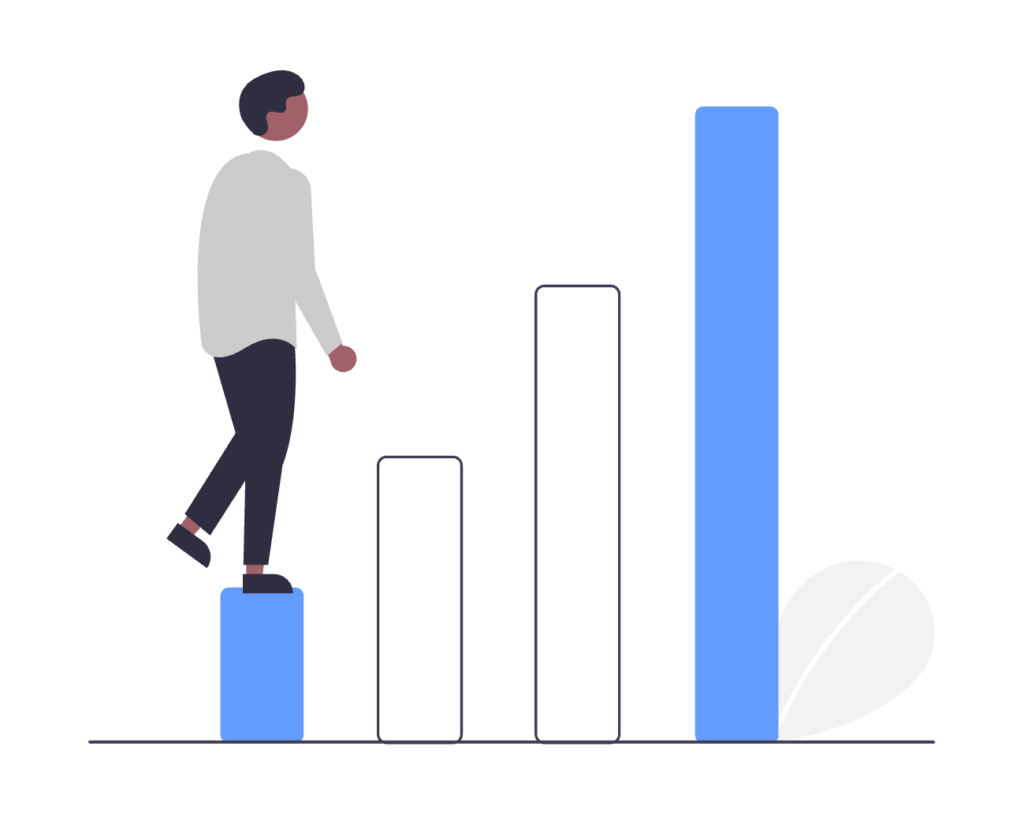
必要なスキルと学習方法
ゲーム業界に入るために必要なスキルは、職種によって異なります。
プランナーなら論理的思考や企画力、
デザイナーならPhotoshopや3DCGソフトの操作、
プログラマーならC#やUnityなどの開発技術が求められます。
未経験の場合、まずは自分が目指す職種を明確にしたうえで、
必要なスキルをリストアップし、オンライン講座や書籍で学習を始めましょう。
独学でもスキルは身につきますが、スクールや専門学校、コミュニティに所属するとモチベーションの維持や情報収集にも役立ちます。
ポートフォリオ・実績の作り方
未経験者にとって最大の武器は「実績の見える化」です。
企画書、デザイン集、プログラムデモ、完成したミニゲーム
自分のスキルを証明できる成果物をポートフォリオにまとめることが重要です。
企業は「どれだけ学んだか」より「何を作れるか」を重視する傾向が強いため、
完璧でなくても良いので自分をアピール出来る作品を用意しましょう。
可能であればGitHubやnoteなどで公開し、第三者に見られる形にしておくと好印象です。
就活・転職活動で重視されるポイント
採用側が見ているのは、スキルの有無だけではありません。
「どれだけゲームに情熱があるか」「チームでの協調性はあるか」「学び続ける姿勢があるか」など、ポテンシャルや人間性も重視されます。
とくに未経験からの挑戦で大切なのは、伸びしろを感じさせる材料をいかに提示できるかです。
志望動機や自己PRで「なぜゲーム業界なのか」を自分の言葉で語れるかが、合否を分ける大きな要素となります。
まとめ:ゲームを仕事にする夢を現実に
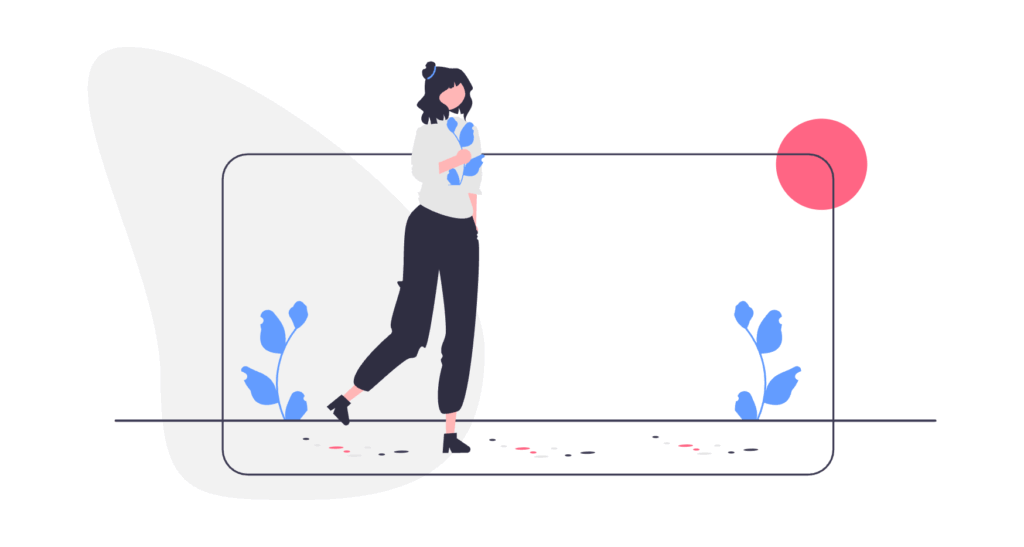
自分に合った働き方を見つける
ゲーム業界には多様な職種やキャリアの選択肢があります。
大手企業での安定志向もあれば、スタートアップでの挑戦志向、さらにはフリーランスや起業といった道も。
大切なのは、「どんな環境で、どんな仲間と、どんなゲームを作りたいか」を自分自身に問い続けること。
正解は人それぞれ違います。自分に合ったスタイルを見つけることが、長く続ける秘訣です。
色んなことやってみて少しずつ確かめていくのが最も早くて分かりやすいですよ。
情熱と継続が生き残りの鍵
技術や才能は、あとからついてきます。
むしろ業界で長く活躍している人ほど、地道に努力を続けてきた人が多いのです。
とくに変化の激しいこの業界では、常に学び続ける姿勢が求められます。
「好き」という情熱が原動力になり、試行錯誤を楽しめる人ほど、長く生き残る傾向にあります。
諦めず、地道に、しかし確実に前進する力こそが最も大きな武器です。
好きを力に変えてプロになる道
「ゲームが好き」
その気持ちは、すべての原点です。
もしその好きを諦めずに追いかけることができたなら、
あなたはすでにプロへの第一歩を踏み出しています。
プロとは、好きなことに責任を持ち、継続的に価値を提供できる人のこと。
はじめの一歩は小さくても構いません。
学び始める、作ってみる、応募してみる
その小さな一歩から私もニートから夢を叶えて
ゲーム会社でゲームを作る仕事を出来るようになりましたから。
ゲーム会社への就職で必要な全てをまとめました↓
最新の情報はXをフォローして確認↓